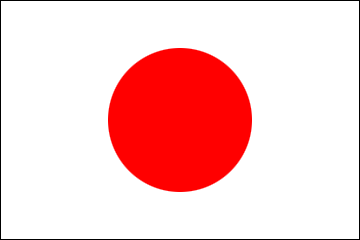変貌する産油国UAE ~新大使の第一印象~
在アラブ首長国連邦 特命全権大使 岡庭 健
(2025年8月発行 日本アラブ首長国連邦協会機関誌UAE78号掲載記事)
(注)本稿は、大使の個人的意見を表したものであり、日本政府の立場を記述するものではありません。

昨年10月末に前任地のケニアからアラブ首長国連邦(以下、「UAE」と言及)に転勤してから7ヶ月半があっという間に過ぎた。過去に国際機関や開発協力を担当した際に中東諸国との関わりはあったが、同地域在勤は初めてである。
これまでに多くの国を見てきたが、UAEは世界でも希なほど国造りに成功している。全人口約1000万人のうちUAE人の人口は120万人(推計値)に過ぎず、日本で言えば広島市と変わらない。数だけでなく技術や専門知識を持つ人材が限られる中、UAEは、外国人材を積極的に受け入れて活用し、最先端の技術や設備を使って各種大型事業を実現している。成功の要因として、莫大な石油収入の存在はもちろんだが、政治の安定や指導層の先見の明と構想力、更には国内で9割近くを占める外国人との共生が挙げられる。湾岸産油国のサウジやカタールも同様に経済多角化に力を入れているが、UAEは一歩も二歩も先んじているように見える。これは、UAEが新たな分野への挑戦により先駆者の利益を目指す傾向があることと関係があるかもしれない。
日本にとってUAEは建国前から一貫して重要な原油の安定供給元であり、また、世界でも数少ない日本の自主開発油田がある国である。近年、両国の関係は、UAEの経済多角化に伴い非石油の分野でも拡大している。また、近年、UAEは国連安保理非常任理事国を務め、COP28やドバイ万博を主催する等国際社会で大きなプレゼンスを発揮している。国際社会の共通の課題に対処する上でも日UAEの協力は重要である。大使としてこのように重要な二国間関係を支える一端を担う責任の重さに身が引き締まる思いである。
当地で多数の人と会談する過程で一つの疑問が湧いた。日本は、石油を「売ってもらっている」のか、それとも「買ってあげている」のか。短期的に見れば、日系企業合弁のアブダビ石油(ADOC)は、アブダビに鉱区使用料を支払い、石油を生産・輸出しており、「売ってもらっている」、また、UAE側から見れば、日本は最大の顧客として石油を「買ってもらっている」ということになる。他方、長期的視点に立てば、ADOCがUAE結成前の1967年にアブダビから鉱区権益を獲得した後、大きなリスクをとって資金と労力を投入し、1973年にようやく原油生産を開始、その後も油価の暴落で収支赤字になっても、あるいは、石油ショックが起きても、生産・供給は途絶えなかった。UAEにとっても日本は安定した収入源であり、また、エネルギー関連の人材育成やインフラ維持管理に大きな貢献を行ってきた。両国の関係は、「売り手」と「買い手」の次元を超えたもので、「信頼」に基づくパートナーシップだと思う。

(1967年12月 利権協定に署名するザーイド・アブダビ首長 ©アブダビ石油)
4月にADOCのムバラス島の海上油田を視察した。初めて見る海上油田では、灼熱の太陽の下、エメラルドの海に浮かぶ人工島で日本人と外国人社員が一丸となって働く姿に感銘を受けた。日本が輸入する石油の約40%がUAE産で、良好な日UAE関係及び関係者の地道な努力により確保されていることは、もっと広く国内で知られるべきである。

(2025年4月 ムバラス島視察 ©アブダビ石油)
引き続き主要産油国の地位を維持するUAEだが、早い時期から経済多角化に取り組んできた。比較的早く石油生産をやめたドバイは、他の首長国に先行して非石油産業の育成に成功を収めている。最近では、7つの首長国の中でも最大の資金力、政治力を有するアブダビが非石油産業の育成に取り組み、成果を挙げている。日本企業にとってもビジネスチャンスである。
1970年代の建国当初のドバイやアブダビの写真を見ると海沿いに砂壁の建造物がまばらにしかない「町」だった。それが今や、前衛的な形の高層ビルや豪華ホテルが林立し、立派な道路や橋が整備されているのは驚異的である。ドバイやアブダビの経済多角化を見ると、以前在勤した米国フロリダ州の開発モデルに似ている。トランプ大統領が豪華ホテルやゴルフ場を所有するので有名になったフロリダ州は、今でこそ全米で4番目に大きな経済規模をもつ州だが、昔は湿地で覆われ人口の少ない辺境地だった。そこにホテルやディズニーワールド等の娯楽施設を作って冬場の観光の目玉にし、州所得税ゼロ等の優遇により東海岸北部から富裕層や企業を誘致し、建設、観光、サービス、金融等の振興につなげた。湿地と砂漠の違いはあるが、ドバイやアブダビも、所得税をゼロにして海外の富裕層や高技能人材を誘致し、観光、住宅、金融等の産業につなげている。海外で戦乱や政情不安、あるいは富裕層課税の動きがある度に政治が安定し、経済が好調なUAEに外国人が流入している。

(1970年 アブダビのグランドモスクを上空から ©UAE国立公文書館)
アブダビ周辺には複数の人工島がある。おそらく浅瀬の海を大型船が通れるよう浚渫し、その際出た大量の砂を有効活用したのだろう。人工島は目的別に開発している。ヤス島は娯楽エリアとして開発し、先日ディズニーランドの進出計画が発表された。ファヒド島は住宅エリアとして豪華マンション群を建設中である。サディヤット島は文化エリアとしてルーブル美術館やグッゲンハイム美術館(本年中に開館予定)等の大型文化施設がある。本年4月には、アブダビの誘致により、同島で日本のデジタル・アート施設「チームラボ・フェノメナ・アブダビ」が開館し、開館式典に参加した。

(2025年4月 観光見本市アラビアントラベルマーケットにてサディヤット島の開発計画模型を視察 ©在アラブ首長国連邦日本国大使館)
現在、アブダビは、文化芸術に力を入れており、新オペラハウス建設とこの国初めての国立管弦楽団結成が進行中である。新管弦楽団には日本人音楽家も応募中と聞いたことがある。音楽に関しては、本年UAE側の招待により、佐渡裕氏の率いる新日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、ピアニストの反田恭平氏、角野隼斗氏が公演のために来訪した。

(2025年2月 佐渡裕氏率いる新日本フィルハーモニー交響楽団と大使公邸にて ©在アラブ首長国連邦日本国大使館)
文化芸術に力を入れる背景には、国民の文化レベル向上に加えて文化産業育成や観光振興等の経済的側面もある。因みに2024年には3000万人の外国人がUAEを訪問したと言われており、当地の文化活動には世界中から人が集まる。また、「チームラボ」進出に見られるようにUAE人は、親日的で、文化含め日本への関心が高い。日本語学習者は増えており、既に複数の高校と大学で日本語教育が行われている他、本年から日本語能力試験がUAE大学で実施予定である。アブダビ日本人学校は、UAE側の要望を受けて2006年からUAE人児童を受入れ、日本人児童と同じ教育を受ける世界で唯一の学校である。一つ残念なのは、こうした両国間の交流が主としてUAE側のイニシアチブで行われていることである。今後、日本の関係者の間で当地事情への理解と関心が高まり、双方向の交流が進むことを期待する。

(2025年6月 UAE大学における日本語能力試験実施覚書き署名式 ©UAE大学)
赴任前にドバイのCOP28主催(2023年)を知った時には驚いた記憶がある。昔、気候変動交渉を担当した時代には、湾岸産油国とは難しい折衝をすることが多かった。着任後、UAEが気候変動対策に真剣に取り組み、温室効果ガス削減のみならず小島嶼国の適応を支援していることを知った。段々分かってきたのは、UAEが将来の石油資源の枯渇も念頭に再生可能エネルギーや水素、アンモニア、更には原子力発電の導入を積極的に進めていることである。アブダビには、IRENA(国際再生可能エネルギー機関)が本部を置き、また、再生可能エネルギー研究開発のために「マスダール・シティ」が整備されている。この国らしい大がかりな構想力と実行力の現れである。
UAEが脱炭素に取り組むのには、この国の比較優位や経済多角化の動機もあり、経済合理性がある。例えば、当地の天候と国土の大部分を占める砂漠は太陽光発電に適しており、また、水素やアンモニアは天然ガスを利用して生産できる他、化石燃料を燃やして排出される二酸化炭素の分離回収・貯留についてはふんだんにある枯れた油田が貯留場所になる。
特に原子力発電については、再生可能エネルギーだけで対応できない安定的電力供給としての役割がある他、UAEが進めるAIデータインフラ整備により急増する電力需要に対応するために重要なのだろう。現在、稼働済みの原発(4基)により電力需要の約25%を賄っている。原発の建設等には、韓国主導の下、東芝が参画している。東日本大地震後、厳しい状況にある日本の原子力産業のためにも応援したい。
2023年に岸田総理(当時)のUAE訪問時に発表した日本の「グローバル・グリーン・エネルギー・ハブ構想」は、日本が中東諸国と協力することによって経済性のある形で脱炭素を進めることを目指す。既にUAEでは日本企業の参画する水素、アンモニア、グリーンスチール案件が複数進行中である。当地を訪問された経団連幹部が述べていたとおり、湾岸のエネルギーを日本まで1万2000キロ運んで、消費する従来のやり方は変えなければならないのかもしれない。今後、大胆な発想により脱炭素に関する協力一層拡大することを期待する。
UAEは、2013年に国家AI(人工知能)戦略を策定し、AI最先端国を目指して研究開発、人材育成、投資促進等を進めている。王族がリードするAI評議会の下、世界初と言われるAI担当国務大臣を任命し、大統領の名前を冠したMBZ・AI大学を設立している。AI企業G42は、傘下にエネルギー、保健医療、衛星・地理空間、生成AI、ビッグデータ解析を担当する子会社を有し、それぞれの分野でAI活用に取り組んでいる。海外からの人材にも熱心で報道によれば2019年から2024年の期間中、UAEは世界で3番目に多いAI技能人材を受け入れたと言われる。ヤス島やサディヤット島では、一般人を乗せた自動運転車の試験運行が行われており、近く実装予定である。
5月のトランプ米大統領の当地訪問に際して、UAE企業MGXが参画し、ソフトバンクも出資する米国「スターゲイト」プロジェクトの下でデータセンターに多額の投資を行い、米国製高性能半導体の確保に合意した。仏や伊でも現地AI企業と協力してデータ関連投資を発表している。
AIが米中競争の一つの焦点となる中、UAEがこの分野で欧米との協力を進めていることは、日本にとっても関心事である。既に日本企業はUAEで保健医療におけるAI活用等に取り組み、また、両国間では、スタートアップに関して協力を推進している。この他、MBZ・AI大学の教授陣には、2名の日本人が在籍し、基礎研究にも貢献している。これらは、いずれもAIデータ関連の大型投資が関わるものではない。AIや半導体に関連してUAEから巨額の投資を受け入れる仕組みは日本にとっても優良案件たりうる。AI関連で両国の協力が一層強化されることが期待される。
この原稿を執筆中の6月中旬以降、イスラエル及び米国とイランの間で核問題をめぐり軍事的応酬が続いている(6月24日、停戦が発効)。日本は同地域に多くの邦人及び日本企業を抱えており、また、エネルギー安定供給の観点からも、ホルムズ海峡の安全航行を含む湾岸地域の平和と安定は極めて重要で、地域の平和と安定を重視する日UAE両国は共通の利益を有している。2022年に日UAE両国は「包括的パートナーシップ・イニシアチブ」(CSPI)を立ち上げた。この枠組みの下で両国が中東情勢や防衛協力について定期的に協議を行っていることは大きな意義がある。
在UAE日本大使として引き続き幅広い分野で両国の協力を後押ししたい。