 |
在アラブ首長国連邦日本国大使館医務室 |
目 次

|
 1. はじめに 1. はじめに  2. UAEの衛生環境 2. UAEの衛生環境
 衛生環境については一口で言えば、まず問題はありません。停電はほとんどありませんし、上下水道の設備は整っています。公共の場所にはごみ籠が数多く設置され、町のごみは清掃されていて、生ごみの収集も定期的に行われています。上水道の水は脱塩した海水や地下水から人工的に作りだされていて、作りだされた時点では完全にきれいです。しかし、下でも説明しますが、各家屋の貯水槽で問題が生じている場合があります。下水道も整っていますが、たまに降る雨に対してはあまり対策がなされていなくて、道格が冠水することがあります。日本でも問題になりますが、公園や道路でのごみの投げ捨てがあり、安い労働力を使って一生懸命清掃をしていますが追いつかない時もあるようです。生活からでる「ごみ」の分別はまったくせずにごみ袋になんでも入れて捨てられます。この点はたいへんおおらかです。 衛生環境については一口で言えば、まず問題はありません。停電はほとんどありませんし、上下水道の設備は整っています。公共の場所にはごみ籠が数多く設置され、町のごみは清掃されていて、生ごみの収集も定期的に行われています。上水道の水は脱塩した海水や地下水から人工的に作りだされていて、作りだされた時点では完全にきれいです。しかし、下でも説明しますが、各家屋の貯水槽で問題が生じている場合があります。下水道も整っていますが、たまに降る雨に対してはあまり対策がなされていなくて、道格が冠水することがあります。日本でも問題になりますが、公園や道路でのごみの投げ捨てがあり、安い労働力を使って一生懸命清掃をしていますが追いつかない時もあるようです。生活からでる「ごみ」の分別はまったくせずにごみ袋になんでも入れて捨てられます。この点はたいへんおおらかです。
 街にはのら猫はいますがのら犬はまずいません。ネズミも海岸の岸壁近く以外ではほとんど見られません。ご心配のサソリや毒へびも市街地にはいません。ごきぶり、蛾、蚊、などはいますが、数は少なく、住居の中で悩まされるということはまずありません。家ダニ、頭しらみが時に発生します。公園に行くと蟻がいて、これは日本のものより少し毒性が強いようですが、もちろん命に関わるようなことはありません。街中の芝生や木立の中では花卉が多いためか最近は蜂も見られるようになりましたが、暑いのと水が少ないのとで基本的に有害動物が生き難い環境です。それでも微生物(細菌、ウイルスなど)はいますから、感染症はあります。しかしこれもいわゆる風土病と言わなければならないようなものはなく、日本にいる時と同じような注意を守っていればまず問題ありません。 街にはのら猫はいますがのら犬はまずいません。ネズミも海岸の岸壁近く以外ではほとんど見られません。ご心配のサソリや毒へびも市街地にはいません。ごきぶり、蛾、蚊、などはいますが、数は少なく、住居の中で悩まされるということはまずありません。家ダニ、頭しらみが時に発生します。公園に行くと蟻がいて、これは日本のものより少し毒性が強いようですが、もちろん命に関わるようなことはありません。街中の芝生や木立の中では花卉が多いためか最近は蜂も見られるようになりましたが、暑いのと水が少ないのとで基本的に有害動物が生き難い環境です。それでも微生物(細菌、ウイルスなど)はいますから、感染症はあります。しかしこれもいわゆる風土病と言わなければならないようなものはなく、日本にいる時と同じような注意を守っていればまず問題ありません。
 以上のようなわけで、衛生面ではまず問題ありません。もちろん常識の範囲内での注意は必要です。外から帰ったら手を洗い、できればうがいをする。生水は飲まない、などです。特に、気温が高くて汗をよくかきますので、シャワーをこまめにあび、水分補給を十分にすることが大切です。 以上のようなわけで、衛生面ではまず問題ありません。もちろん常識の範囲内での注意は必要です。外から帰ったら手を洗い、できればうがいをする。生水は飲まない、などです。特に、気温が高くて汗をよくかきますので、シャワーをこまめにあび、水分補給を十分にすることが大切です。
 下の日常生活上の注意の項でさらに詳しくご説明をします。 下の日常生活上の注意の項でさらに詳しくご説明をします。
  

 3. UAEの医療環境 3. UAEの医療環境
(1)病院の仕組み
 UAEでも日本と同じように公立(国立及び各首長国立)の病院と私立病院とがあります。2006年より医療保険の導入が始まり、当国で働く場合、スポンサーが被保険者となり医療保険に加入することが必要になりました。これによって以前は100%自費で受診していた私立病院も、保険を利用して安く受診できるようになりました。 UAEでも日本と同じように公立(国立及び各首長国立)の病院と私立病院とがあります。2006年より医療保険の導入が始まり、当国で働く場合、スポンサーが被保険者となり医療保険に加入することが必要になりました。これによって以前は100%自費で受診していた私立病院も、保険を利用して安く受診できるようになりました。
 私立病院には総合病院から、町の開業医のレベルまでたくさんあります。日本人会の婦人部が作っている病院リストもありますが、皆様の間でいろいろ口込み情報があると思いますので、そうした情報に基づいて受診先を選ぶと良いと思います。邦人の場合は、ほとんどの方がまずは私立病院を受診するようです。ここで大抵は問題が解決しますが、手術が必要と言われ、急遽帰国するということもあるようです。 私立病院には総合病院から、町の開業医のレベルまでたくさんあります。日本人会の婦人部が作っている病院リストもありますが、皆様の間でいろいろ口込み情報があると思いますので、そうした情報に基づいて受診先を選ぶと良いと思います。邦人の場合は、ほとんどの方がまずは私立病院を受診するようです。ここで大抵は問題が解決しますが、手術が必要と言われ、急遽帰国するということもあるようです。
 当国の国立病院は立派な設備を備え、手術もかなり高度なことが出来るようです。また日本にはないような大きな産科専門病院もあります。しかし問題は、日本のようにきちんとした心遣いができておらず、食事を始め、いろいろ要求してやっとやってもらえることが多いことです。また病院によっては医療保険に加入していなければ診療を拒否される場合もあります。交通事故などで外傷の場合には、救急車で国立病院の救急室へ運ばれますので、医療保険に加入しているかどうか必ず確認することをお勧めします。 当国の国立病院は立派な設備を備え、手術もかなり高度なことが出来るようです。また日本にはないような大きな産科専門病院もあります。しかし問題は、日本のようにきちんとした心遣いができておらず、食事を始め、いろいろ要求してやっとやってもらえることが多いことです。また病院によっては医療保険に加入していなければ診療を拒否される場合もあります。交通事故などで外傷の場合には、救急車で国立病院の救急室へ運ばれますので、医療保険に加入しているかどうか必ず確認することをお勧めします。
(3)医療費
 医療保険制度の導入に伴い、治療費の均一化が行われており、国立病院と私立病院とではあまり医療費に差はないはずです。しかし病院間では多少の違いはあるようです。 医療保険制度の導入に伴い、治療費の均一化が行われており、国立病院と私立病院とではあまり医療費に差はないはずです。しかし病院間では多少の違いはあるようです。
(5)歯科について
 国内には歯科もたくさんあります。国全体としては歯科医が不足しているとの情報もありますが、都市部にはたくさん歯科診療所があります。ヘルスセンタ-内、民間病院内、および開業の歯科医です。ほとんどの邦人の方は開業の歯科医にかかっているようですが、民間病院内の歯科もそれなりのレベルです。しかも治療費は、特殊材料を用いる治療であっても、保険の問題がある日本よりは安いと思います。日本払い戻しのことを十分確認されてから、評判の良い歯科医に治療してもらうと良いと思います。日本よりも短期間でやってくれます。 国内には歯科もたくさんあります。国全体としては歯科医が不足しているとの情報もありますが、都市部にはたくさん歯科診療所があります。ヘルスセンタ-内、民間病院内、および開業の歯科医です。ほとんどの邦人の方は開業の歯科医にかかっているようですが、民間病院内の歯科もそれなりのレベルです。しかも治療費は、特殊材料を用いる治療であっても、保険の問題がある日本よりは安いと思います。日本払い戻しのことを十分確認されてから、評判の良い歯科医に治療してもらうと良いと思います。日本よりも短期間でやってくれます。
(6)緊急かつ重症の場合
 急病や事故での怪我の場合、それが重症であれば、救急車で国立病院の救急室に運ばれます。もちろんそこで治療が開始されますが、安心してかつ高度な治療を受けることのできる文明国または日本に移送したいということがあるかもしれません。こうした場合に備えて、SOSとかEAJという保険に加入している方も多いと思います。しかし、緊急時にはいろいろなことが混乱しますから、日頃からいざという時のために、マニュアルを作っておくことが必要であると考えます。マラリアとか重症肝炎などの場合にはすみやかに判断と行動をする必要があります。 急病や事故での怪我の場合、それが重症であれば、救急車で国立病院の救急室に運ばれます。もちろんそこで治療が開始されますが、安心してかつ高度な治療を受けることのできる文明国または日本に移送したいということがあるかもしれません。こうした場合に備えて、SOSとかEAJという保険に加入している方も多いと思います。しかし、緊急時にはいろいろなことが混乱しますから、日頃からいざという時のために、マニュアルを作っておくことが必要であると考えます。マラリアとか重症肝炎などの場合にはすみやかに判断と行動をする必要があります。
 輸血が必要になる場合もあるかもしれません。当国では輸血用の血液はエイズ,B型およびC型肝炎を含めて、日本と同じレベルでチェックされています。したがって、原則的に輸血を受けても大丈夫です。ただ、輸血に関しては日本国内であっても抵抗感を持っている人がいると思います。この場合には輸血の必要性を十分確認し、納得してから輸血を受けるようにするしかありません。 輸血が必要になる場合もあるかもしれません。当国では輸血用の血液はエイズ,B型およびC型肝炎を含めて、日本と同じレベルでチェックされています。したがって、原則的に輸血を受けても大丈夫です。ただ、輸血に関しては日本国内であっても抵抗感を持っている人がいると思います。この場合には輸血の必要性を十分確認し、納得してから輸血を受けるようにするしかありません。
  

 4. 日常生活上の注意 4. 日常生活上の注意
(2)交通事故
 当国では死因の第二位が事故死です。「交通事故に注意する」というのはあまり医学的なことではないのですが、ご注意申し上げておいていけないことはないと思います。車の運転が結構乱暴で、スピードが出ていますので、いったん事故が起こると大怪我になります。幸い邦人の大事故は今までありませんでしたが、当国人の特に若者はひどい怪我をして運びこまれることが多いようです。地元の外科医と話しているとそのことが話題になります。 当国では死因の第二位が事故死です。「交通事故に注意する」というのはあまり医学的なことではないのですが、ご注意申し上げておいていけないことはないと思います。車の運転が結構乱暴で、スピードが出ていますので、いったん事故が起こると大怪我になります。幸い邦人の大事故は今までありませんでしたが、当国人の特に若者はひどい怪我をして運びこまれることが多いようです。地元の外科医と話しているとそのことが話題になります。
 乱暴な運転をしないことはもちろんのこと、道路にある「ハンプス」には十分注意しましょう。また少しでも郊外にドライブに出かける時には売店の数が少ないことに加え、パンクなどで炎天下で長時間過ごさねばならない危険もあり、必ずミネラルウォーターのボトルを持って行き脱水にならないように気をつけて下さい。 乱暴な運転をしないことはもちろんのこと、道路にある「ハンプス」には十分注意しましょう。また少しでも郊外にドライブに出かける時には売店の数が少ないことに加え、パンクなどで炎天下で長時間過ごさねばならない危険もあり、必ずミネラルウォーターのボトルを持って行き脱水にならないように気をつけて下さい。
(3)紫外線
 当国はほとんど毎日が晴れで、景色や建物は白色が基調になっています。こうした特殊な条件下で、紫外線がたいへん氾濫しやすくなっています。紫外線はビタミンDの合成に役立つなど健康維持にとって大切なものですが、浴びすぎるとたいへん有害なものでもあります。紫外線の有害作用は大きく分けて二つあります。皮膚に対するものと、目に対するものです。 当国はほとんど毎日が晴れで、景色や建物は白色が基調になっています。こうした特殊な条件下で、紫外線がたいへん氾濫しやすくなっています。紫外線はビタミンDの合成に役立つなど健康維持にとって大切なものですが、浴びすぎるとたいへん有害なものでもあります。紫外線の有害作用は大きく分けて二つあります。皮膚に対するものと、目に対するものです。
 皮膚に対するものとしてはもちろん日焼けです。当地では日ざしがたいへん強いので、あっという間に激しく日焼けします。外に出る時には、長柚シャツ、長ズボン、帽子といういでたちがお勧めです。日焼けはくり返されると皮膚の老化を促進しますし、中年以降では皮膚ガンの可能性も多少あります。 目については白目が充血して炎症が起きます。これは結膜炎で、目を休めたり、目薬をつけたりする必要があります。良期間にわたって紫外線にさらされていると、白内障や網膜症が起さてくることもあります。外出の際は色が濃いめのサングラスを着用するのが良いでしょう。 皮膚に対するものとしてはもちろん日焼けです。当地では日ざしがたいへん強いので、あっという間に激しく日焼けします。外に出る時には、長柚シャツ、長ズボン、帽子といういでたちがお勧めです。日焼けはくり返されると皮膚の老化を促進しますし、中年以降では皮膚ガンの可能性も多少あります。 目については白目が充血して炎症が起きます。これは結膜炎で、目を休めたり、目薬をつけたりする必要があります。良期間にわたって紫外線にさらされていると、白内障や網膜症が起さてくることもあります。外出の際は色が濃いめのサングラスを着用するのが良いでしょう。
(4)熱中症
 熱中症とは、従来熱射病、日射病などと呼ばれていた夏期に多い代謝障害を総称する呼び方です。つまり、熱射病とは高温環境下に長く晒されて体内に熱が溜まってしまって高体温、無汗、意識低下などの症状を呈するものを言います。日射病とは日射に長時間さらされて同じ症状を呈するものを言います。この他に、熱疲労と言って、高温多湿環境に晒されて、多汗皮膚湿潤状態になり、体表はむしろ冷たくなっているという状態もあります。簡単に言えば、休憩も取らずに水分の補給も不十分なまま炎天下で長時間運動を続けて、その結果として頭痛、めまいなどが出てきて、さらにそのまま頑張ると吐いたり、呼吸が苦しくなったりするのが熱中症です。 熱中症とは、従来熱射病、日射病などと呼ばれていた夏期に多い代謝障害を総称する呼び方です。つまり、熱射病とは高温環境下に長く晒されて体内に熱が溜まってしまって高体温、無汗、意識低下などの症状を呈するものを言います。日射病とは日射に長時間さらされて同じ症状を呈するものを言います。この他に、熱疲労と言って、高温多湿環境に晒されて、多汗皮膚湿潤状態になり、体表はむしろ冷たくなっているという状態もあります。簡単に言えば、休憩も取らずに水分の補給も不十分なまま炎天下で長時間運動を続けて、その結果として頭痛、めまいなどが出てきて、さらにそのまま頑張ると吐いたり、呼吸が苦しくなったりするのが熱中症です。
 熱中症を予防するためには、酷暑の時間帯ははずす、帽子などで日よけをする、のどが乾く前に適宜水分を補給するようにする、などが大切です。特にゴルフなどの時には、お互いに観察しあって調子が悪そうな人がいたら休ませることが必要です。もし熱中症になってしまったら、まずは体を冷やす(送風、氷枕)、水分補給をする、そしてゆっくり体を休めることが大切です。 熱中症を予防するためには、酷暑の時間帯ははずす、帽子などで日よけをする、のどが乾く前に適宜水分を補給するようにする、などが大切です。特にゴルフなどの時には、お互いに観察しあって調子が悪そうな人がいたら休ませることが必要です。もし熱中症になってしまったら、まずは体を冷やす(送風、氷枕)、水分補給をする、そしてゆっくり体を休めることが大切です。
 5. 海外生活上の注意 5. 海外生活上の注意  6. 子供の病気 6. 子供の病気
 どこの国でも子どもの病気で多いのは感染症です。当国では、水痘の予防接種が一般的に行われていないため、特に水痘が多いようです。ふだん健康で重大な基礎疾患のないお子さんの場合には、これにかかっても重大な結果になることはまずありませんから心配はいらないと思います。これ以外の感染症は、当国の定型的な予防接種を受けていればまず大丈夫です どこの国でも子どもの病気で多いのは感染症です。当国では、水痘の予防接種が一般的に行われていないため、特に水痘が多いようです。ふだん健康で重大な基礎疾患のないお子さんの場合には、これにかかっても重大な結果になることはまずありませんから心配はいらないと思います。これ以外の感染症は、当国の定型的な予防接種を受けていればまず大丈夫です
 これら以外の病気としては、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー性疾患、スポーツや成長に伴う関節や軟部組織の痛み、耳鼻科関係の疾患などが問題として多いと思います。これらは個々に対処していく必要があります。 これら以外の病気としては、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー性疾患、スポーツや成長に伴う関節や軟部組織の痛み、耳鼻科関係の疾患などが問題として多いと思います。これらは個々に対処していく必要があります。
日本では平成7年4月から予防接種の施行方法が改正され、
従来の集団接種から個別の任意接種へと変わりました。
 当国では基本的に任意個別接種ですが、日本といくぶん違った種類、回数の予防接種を行っています。しかし、WHOの勧めるスケジュールに沿っており、問題はありません。日本でのように親切な案内などは来ませんので、自分から病院に行かないと接種を受けられません。接種料金は実費払いになります。予防接種の対象になるお子さんをお持ちの方はかかりつけの小児科医を決めておいて相談されるとよいと思います。 当国では基本的に任意個別接種ですが、日本といくぶん違った種類、回数の予防接種を行っています。しかし、WHOの勧めるスケジュールに沿っており、問題はありません。日本でのように親切な案内などは来ませんので、自分から病院に行かないと接種を受けられません。接種料金は実費払いになります。予防接種の対象になるお子さんをお持ちの方はかかりつけの小児科医を決めておいて相談されるとよいと思います。
出生時 |
BCG、HBV-1 |
生後1ヶ月 |
HBV-2 |
生後2ヶ月 |
OPV-1、DPT-1、HIB-1 |
生後4ヶ月 |
OPV-2、DPT-2、HIB-2 |
生後6ヶ月 |
OPV-3、DPT-3、HIB-3 |
生後8ヶ月 |
麻疹、HBV-3 |
生後15ヶ月 |
MMR、HIB |
生後18ヶ月 |
OPV-4、DPT-4 |
6歳 |
OPV-5、DT、MMR |
12歳 |
風疹 |
(HBV: B型肝炎、OPV: 経口ポリオワクチン、HIB: インフルエンザ菌ワクチン、D: ジフテリア、P: 百日咳、T: 破傷風、M: 流行性耳下腺炎、M: 麻疹、R: 風疹 ) |
| *水痘は必要により接種 |
。
  

 7. 成人の病気 7. 成人の病気
 成人がなる病気にはありとあらゆるものがあって、とてもすべては説明しきれません。ここではいわゆる成人病と成人がかかりやすい感染症について説明します。 成人がなる病気にはありとあらゆるものがあって、とてもすべては説明しきれません。ここではいわゆる成人病と成人がかかりやすい感染症について説明します。
 まず成人病ですが、それらには高血糖症(糖尿病)、高脂血症、高血圧症、高尿酸血症、そしてこれらすべての基礎としての肥満があります。日常生活上の注意の項でもご説明しましたが、高栄養と運動不足のために、当国での生活はどうしても成人病を引き起こしやすくなります。上に挙げた成人病はなぜいけないかと言いますと、これらすへては「血管の老化」を引き起こすからです。血管が痛むと心臓や脳といったきわめて大切な臓器に障害がでます。また糖尿病のもっとも恐ろしい合併症は眼とか腎臓の血管が傷んで機能障害を起こしてくることです。 まず成人病ですが、それらには高血糖症(糖尿病)、高脂血症、高血圧症、高尿酸血症、そしてこれらすべての基礎としての肥満があります。日常生活上の注意の項でもご説明しましたが、高栄養と運動不足のために、当国での生活はどうしても成人病を引き起こしやすくなります。上に挙げた成人病はなぜいけないかと言いますと、これらすへては「血管の老化」を引き起こすからです。血管が痛むと心臓や脳といったきわめて大切な臓器に障害がでます。また糖尿病のもっとも恐ろしい合併症は眼とか腎臓の血管が傷んで機能障害を起こしてくることです。
 ここでは特に肥満についてご説明します。肥満している人はそうでない人に比べて、脳血管障害、心臓疾患、肝硬変などで死亡することが多く、糖尿病、心臓病、肝胆疾患などで入院することが多いと言われています。 ここでは特に肥満についてご説明します。肥満している人はそうでない人に比べて、脳血管障害、心臓疾患、肝硬変などで死亡することが多く、糖尿病、心臓病、肝胆疾患などで入院することが多いと言われています。
 肥満度の計算方法は、下のBMI(Body Mass Index)がよく使われていますので、各人計算してみられるとよいと思います。 肥満度の計算方法は、下のBMI(Body Mass Index)がよく使われていますので、各人計算してみられるとよいと思います。
BMI:Body Weight(kg)/[Body Length(m)]2 |
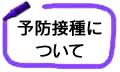
成人の予防接種に関しては以下のようにたくさんのものがあります。
簡単に説明しておきますので、必要に応じて受けて下さい。
| A型肝炎 |
経口感染しますので、衛生状態の悪い土地へ出かける場合には受けておくほうが良いでしょう。特に生ものを食べる場合には要注意です。 |
| B型肝炎 |
医療行為、特に手術や輸血の際に危険です。免疫をもっていて悪いことはないので、もし抗体をもっていないようでしたら、予防接種を受けておくほうが安心です。 |
| コレラ |
コレラワクチンは効果が長続きしないので、WHOは接種をすすめていません。 |
| ペスト |
ペストワクチンは副作用が強いので特殊な場合以外は使われていません。 |
| チフス |
最近経口ワクチンが開発されました。流行地へ出かける場合には予防するほうが良いでしょう。 |
髄膜炎菌性
髄膜炎 |
細菌性の髄膜炎が、特にハッジ(聖地巡礼)の時に流行します。流行地へ出かける場合に予防注射が必要です。 |
| 黄熟病 |
アフリカの国の中では入国に際して予防接種を義務づけているところがあります。この予防接種だけは病院ではなく、検疫所でしか受けられません。 |
| 狂犬病 |
アフリカや南米では心配があります。特に動物に接触する人は必須です。 |
| 日本脳炎 |
小児期に予防接種することになっていますが、東南アジアなどの流行地の農村部に滞在する場合には必要になります(豚のいない所では不必要)。 |
| 破傷風 |
土や砂で汚れた傷では感染の可能性があります。やはり小児期に予防接種することになっていますが、動物の糞便などが見られる土地で怪我をしたら直後にトキソイドを注射しておく方が無難です。 |
| インフルエンザ杆菌 |
いままでのワクチンはあまり有効でないものが多かったのですが、改良が進んだようですので、流行地へ行く場合には受ける方がよいでしょう。 |
ヴィールス性
インフルエンザ |
検査法、薬物治療法共に格段の進歩が見られ、ワクチンの効果も優れています。 |
| マラリア |
マラリアの予防薬は内服薬です。マラリアの汚染地区へ出かける場合にはぜひ使用して下さい。どの地域へでかけるかによって薬が違ってきますので、必要な場合には大使館医務室に問い合わせて下さい。しかしなんと言っても大切なのは、蚊に刺されないようにすることです。厚手の布製の長袖シャツや長ズボンを着用し、昆虫忌避剤や蚊帳を使用し、夕方から夜間かけて活動するはまだら蚊を避ける工夫が必要です。 |
。
  

 8. 家庭での応急処置 8. 家庭での応急処置
(1)発熱
 一般的には体のどこかに炎症が起きていると発熱します。原因は細菌やウイルスの他いろいろありますから、単に熱が出たといって軽くみることは危険です。また、熱がでたらさませば良いというほど簡単なものでもありません。発熱は体からの危険信号を意味すると同時に、最良の治療効果も持っています。良くわからない場合には医師に相談して下さい。 一般的には体のどこかに炎症が起きていると発熱します。原因は細菌やウイルスの他いろいろありますから、単に熱が出たといって軽くみることは危険です。また、熱がでたらさませば良いというほど簡単なものでもありません。発熱は体からの危険信号を意味すると同時に、最良の治療効果も持っています。良くわからない場合には医師に相談して下さい。
 発熱の原因としていちばん多いのはウイルス感染による風邪(感冒)です。これには特効薬はありませんから、三日ほど風邪薬をのみながら安静療養すれば、たいていは解熱して回復します。氷枕で頭を冷やすことも有効です。大量に汗をかくようになれば回復も間もなくです。 発熱の原因としていちばん多いのはウイルス感染による風邪(感冒)です。これには特効薬はありませんから、三日ほど風邪薬をのみながら安静療養すれば、たいていは解熱して回復します。氷枕で頭を冷やすことも有効です。大量に汗をかくようになれば回復も間もなくです。
 発熱に喉の痛みを伴えば急性扁桃炎か急性咽頭炎です。強い咳や胸痛が伴えば気管支炎や肺炎を考えます。この場合には解熱剤だけでなく、抗生物質が必要になることがあります。しかし細菌感染が認められない内に抗生物質をしろうと判断で使うことには問題がありますので、必ず医師に相談してからにして下さい。 発熱に喉の痛みを伴えば急性扁桃炎か急性咽頭炎です。強い咳や胸痛が伴えば気管支炎や肺炎を考えます。この場合には解熱剤だけでなく、抗生物質が必要になることがあります。しかし細菌感染が認められない内に抗生物質をしろうと判断で使うことには問題がありますので、必ず医師に相談してからにして下さい。
(2)下痢
 下痢になったらまず大切なことは水分補給です。少なくとも出た分だけは補給する必要があります。この場合には、ただのミネラルウォーターではなく、ポカリスウェットなどのスポーツドリンクや、薬局で売っている水分補給用のパウダー(ORS:Oral rehydration solution)を用いるとよいでしょう。もし手元にあれば、整腸剤を使ってみるのも良いでしょう。 下痢になったらまず大切なことは水分補給です。少なくとも出た分だけは補給する必要があります。この場合には、ただのミネラルウォーターではなく、ポカリスウェットなどのスポーツドリンクや、薬局で売っている水分補給用のパウダー(ORS:Oral rehydration solution)を用いるとよいでしょう。もし手元にあれば、整腸剤を使ってみるのも良いでしょう。
 しかし、下痢便に血液が混じる、激しい腹痛があって発熱している、吐き気があったり実際に吐いているなどの場合には、医師の診察を受ける必要があります。特にロから水分補給できない時には危険ですから、すぐに医師に連路して下さい。 しかし、下痢便に血液が混じる、激しい腹痛があって発熱している、吐き気があったり実際に吐いているなどの場合には、医師の診察を受ける必要があります。特にロから水分補給できない時には危険ですから、すぐに医師に連路して下さい。
(4)鼻血
 鼻血は子供ではよくみられるものです。鼻をいじりすぎたり、風邪で鼻の粘膜が傷んでいたりすると出血します。鼻血は鼻中隔(左右の鼻の穴の問のしきり)の粘膜で、小鼻をつまんで圧迫できる部位から出ていることがほとんどです。したがって鼻をつまんで圧迫すればよいのですが、この場合に小さめ(ちょうど鼻の穴の大きさ)の脱脂綿を挿入してから、圧迫すると良いでしょう。しかし、乾燥した脱脂綿ではくっついてしまって後で取ろうとすると再出血することもありますので、手元に消毒薬があれば、脱脂綿をこれに浸して軽くしぼって入れ直すとよいかもしれません。また、鼻の上から濡れタオルをかけたり、上着のぼたんをはずしてリラックスさせたりするのも良いでしょう。 鼻血は子供ではよくみられるものです。鼻をいじりすぎたり、風邪で鼻の粘膜が傷んでいたりすると出血します。鼻血は鼻中隔(左右の鼻の穴の問のしきり)の粘膜で、小鼻をつまんで圧迫できる部位から出ていることがほとんどです。したがって鼻をつまんで圧迫すればよいのですが、この場合に小さめ(ちょうど鼻の穴の大きさ)の脱脂綿を挿入してから、圧迫すると良いでしょう。しかし、乾燥した脱脂綿ではくっついてしまって後で取ろうとすると再出血することもありますので、手元に消毒薬があれば、脱脂綿をこれに浸して軽くしぼって入れ直すとよいかもしれません。また、鼻の上から濡れタオルをかけたり、上着のぼたんをはずしてリラックスさせたりするのも良いでしょう。
 出血が多量でなかなか止まらない場合には耳鼻科に駆け込む必要があります。 出血が多量でなかなか止まらない場合には耳鼻科に駆け込む必要があります。
(5)痛み
 痛みも発熱と同じで、体になんらかの異常がある場合の警告です。一般的には安静、鎮痛剤、湿布などで様子をみますが、漫然と痛み止めを使うことはぜひ避けるべきです。重大な病気が潜んでいて、これを見逃す危険牲があるからです。
痛む部位が固定していて、しかもだんだんひどくなる場合には特に要注意です。例えば、右下腹部の痛みは盲腸炎(正しくは虫垂炎)、背中の痛みは腎結石というぐあいです。特に注意すべきは頭痛で、脳腫瘍やくも膜下出血などが隠れている場合があります。痛む部位が同じであって、発熱や下痢を伴う場合には医師の診察を受けて下さい。 痛みも発熱と同じで、体になんらかの異常がある場合の警告です。一般的には安静、鎮痛剤、湿布などで様子をみますが、漫然と痛み止めを使うことはぜひ避けるべきです。重大な病気が潜んでいて、これを見逃す危険牲があるからです。
痛む部位が固定していて、しかもだんだんひどくなる場合には特に要注意です。例えば、右下腹部の痛みは盲腸炎(正しくは虫垂炎)、背中の痛みは腎結石というぐあいです。特に注意すべきは頭痛で、脳腫瘍やくも膜下出血などが隠れている場合があります。痛む部位が同じであって、発熱や下痢を伴う場合には医師の診察を受けて下さい。
 当国のように暑いところでは頭痛を感じることが多くなります。これは大量の発汗のために水分と電解質が失われて脱水状態になるためです。水分を補給して涼しい所で休む必要があります。 当国のように暑いところでは頭痛を感じることが多くなります。これは大量の発汗のために水分と電解質が失われて脱水状態になるためです。水分を補給して涼しい所で休む必要があります。
  

 9. おわりに 9. おわりに
 アラブ首長国連邦の生活環境、特に気象は日本とは全く異なっています。しかし、邦人の方々はおおむね健康に過ごされています。それはやはり日本との違いを十分に頭に入れて、健康に十分留意しておられる結果
だと思います。当国ではその暑さとイスラムの慣習からだと思いますが、日中の一時から五時の間は昼休みということになっています。この間に昼寝をするのでしょう。夕方五時からはもう一仕事ということになり、夕食が遅い時間になります。「郷に入っては郷に従え」というわけで、私たちも昼寝をし、アザーン(お祈りの呼びかけ)を聞きながら、当地の生活スタイルに合わせて暮らすのが賢明なので
はないでしょうか。 アラブ首長国連邦の生活環境、特に気象は日本とは全く異なっています。しかし、邦人の方々はおおむね健康に過ごされています。それはやはり日本との違いを十分に頭に入れて、健康に十分留意しておられる結果
だと思います。当国ではその暑さとイスラムの慣習からだと思いますが、日中の一時から五時の間は昼休みということになっています。この間に昼寝をするのでしょう。夕方五時からはもう一仕事ということになり、夕食が遅い時間になります。「郷に入っては郷に従え」というわけで、私たちも昼寝をし、アザーン(お祈りの呼びかけ)を聞きながら、当地の生活スタイルに合わせて暮らすのが賢明なので
はないでしょうか。
 当国は日本に比べれば、医療面、特に予防医学や福祉面
で、まだまだ遅れています。医療の質を上げるための努力もかなりなされていますが、これからという点も多々あります。こうした環境ですので、本小冊子が「ころばぬ
先の杖」として少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。 当国は日本に比べれば、医療面、特に予防医学や福祉面
で、まだまだ遅れています。医療の質を上げるための努力もかなりなされていますが、これからという点も多々あります。こうした環境ですので、本小冊子が「ころばぬ
先の杖」として少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
 大使館の医務室ではいろいろな医療相談をお受けしています。どんなことでもお困りのことがありましたらご連絡下さい。ただし、診療については、すべてについて診断や治療はできかねますので、地元の病院をご紹介することになる場合があります。この場合にはお差し支えのない範囲で病院へご一緒させていただくよう努力しています。なお、ご相談いただいた場合、特に医務室で治療までさせていただいた場合には、経過のことが気になりますので、結果
をご一報いただけたらたいへん幸いと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 大使館の医務室ではいろいろな医療相談をお受けしています。どんなことでもお困りのことがありましたらご連絡下さい。ただし、診療については、すべてについて診断や治療はできかねますので、地元の病院をご紹介することになる場合があります。この場合にはお差し支えのない範囲で病院へご一緒させていただくよう努力しています。なお、ご相談いただいた場合、特に医務室で治療までさせていただいた場合には、経過のことが気になりますので、結果
をご一報いただけたらたいへん幸いと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
  

|



